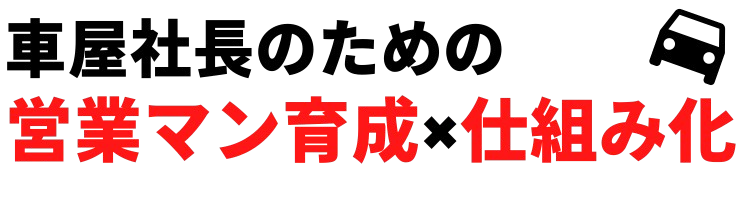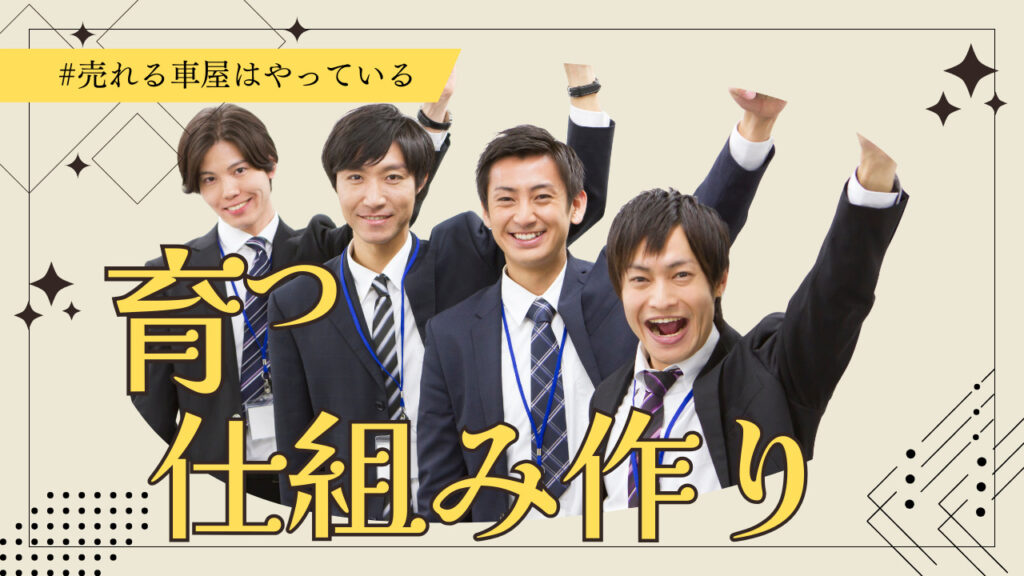こんにちは、野瀬です。
人材育成を考えているのですが、なかなかうまくいかなくて…
社員はすぐに辞めるし、売上を作っているのはエースの営業マン1人だけ。
何度もそのエースのような営業ができないかと考えたのですが、何を教えていいのか分からず結局会社としてそれなりに売上は上がっているので、ずるずるとそのままになってしまっています。
でも、会社の未来を考えた時に、辞められたら売上は間違いなく下がります。
そして、このエースの営業マンが作る以上の売上アップは見込めません。
これでは、会社組織とも言えず1人の力に依存している状態をなんとか脱却したいんです。
このように考えている社長は少なくないのではないでしょうか?
会社をこれから先10年、20年と継続していく未来を考えた時に、確かに1人の力に頼り続けている社長は不安が大きいと思います。
もし辞めてしまったら売上がなくなってしまう。
こんなことを考えながら経営をしていたら、人を育てて強い組織を作る!と思っていてもなかなかできないですよね。
私が、「売れる」車屋になるためにいつもお伝えしていることは、「人を育てる」方法ではありません。
どんな社員でも売れる営業マンに変貌する「育つノウハウ」を社内に残すことです。
そうすれば、たとえ営業マンが辞めても売上が下がることありません。
むしろ、トップ営業マンに頼らずとも、売上が今よりも大きくアップさせることも可能なのです。
関連記事
トップ営業マン依存は会社の崩壊リスク!車屋の社長が右腕探しより営業の仕組み化を急ぐべき理由
売れる車屋が実践している「育つノウハウ」とは?
私がお伝えしている「育つノウハウ」とは、決して特別な営業トークや飛び抜けたセンスではありません。
むしろ「誰でも同じように実践できる再現性のある型」を社内に残していくことです。
例えば、来店されたお客様にどんな声かけをするのか。試乗で何を説明するのか。
見積もり提示の順番や言葉の選び方など、エース営業マンが感覚でやっている行動を、仕組みとして残すのです。
「育てる」から「育つ」への発想転換
多くの社長は「社員を育てよう」としますが、教育には時間も労力もかかり、相手のやる気や適性にも左右されます。
結果として社長や店長が疲弊し、続かないケースが多いのです。
だからこそ必要なのは、エース営業マンのやり方を見える化し、再現可能な形に落とし込むこと。
教育ではなく仕組みを整えることで、誰でも成果を出せる環境が自然と生まれます。
関連記事
売れる営業マンを採用するのではなく、育てる仕組みをつくるべき理由
営業の仕組み化はスポーツの練習と同じ
営業の仕組み化は、スポーツに例えると分かりやすいでしょう。
「プロ選手のセンス」を教えることはできなくても、「この練習をすればシュート成功率が上がる」という手順なら共有できます。
営業も同じで、
- 来店前の電話での確認事項
- 初回接客でお客様に安心してもらうための流れ
- 成約までに踏むべきステップ
これらを整理し、マニュアルやチェックリストとして仕組みにすれば、新人でもすぐに結果を出せるようになります。
大事なことは、売るための手順を教えることです。
売上の安定と拡大につながる
営業の仕組み化の最大のメリットは、売上の安定と利益の拡大です。
トップ営業マンが辞めても売上は落ちず、むしろ複数の営業マンが同じ成果を出せるようになることで、会社全体の売上は積み上がります。
さらに社長自身も「辞められたらどうしよう」という不安から解放され、未来を安心して描けるようになります。
経営者が精神的に余裕を持てるからこそ、新しい挑戦や事業展開にも前向きになれるのです。
このようにしていくことで、強い組織として持続可能な経営にシフトしていくことができます。
関連記事
99%の車屋社長ができない中古車1台あたりの粗利を2倍にする「価値向上戦略」
「人を育てる」方法から「育つ仕組み」を残す
売れる車屋が強い組織に変貌している理由は、ただの偶然や社員の才能ではありません。
人を育てるという考え方に依存せず、誰がやっても成果を出せる「育つ仕組み」を社内に残しているからです。
エースに頼り切った経営は、常に「もし辞めたら…」という不安と隣り合わせです。
ですが、仕組みを残せばその不安は消え、むしろどの社員からも新しいエースが生まれる土台ができます。
これこそが「営業の仕組み化」の本質であり、車屋が10年先、20年先もお客様から選ばれ続けるための未来を支える最大の武器です。
社員一人ひとりが自然と育ち、会社全体が勝手に強くなっていく。
そんな「仕組み経営」に舵を切れるかどうかが、これからの車屋経営を分ける最大の分岐点だと私は思います。
営業の仕組み化を少しでも知りたい!と思った社長はぜひこちらの書籍を一読いただけたらと思います。
まずは、こちらの書籍に私が行ってきたことが全て書かれています。
▶『車屋経営のマル秘戦略』